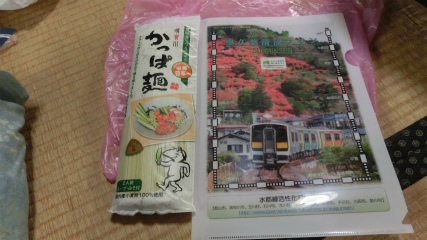2013年8月25日 リゾート奥久慈清流号乗車記
今夏の臨時列車リリースの中に、水郡線 郡山〜常陸大子間を「リゾート奥久慈清流号」というキハ48形クルージングトレインが運転されるいう情報を発見。
この区間で臨時列車が運転されるのは珍しく、当然ながら私も是非乗りたいということで乗車してきました。
全車指定席で席数少なく珍しい区間ということで確保がやや難しいところでしたが、無事確保に成功。
予想通り発売開始時刻の10時ちょっと過ぎにたちまち完売したとのことです。
しかし、残念ながら8/24は都合が悪く、25日も午後から地元の行事に参加しなければならなかったため往路の郡山→磐城塙のみと乗車となりました。
6月に連続で旅行したこともあり、今年は異例の夏の18きっぷ購入不要年となったため乗車券は普通に購入しての乗り鉄となりました。
水郡線最寄り駅から325Dでゆっくりと郡山へ向かいます。
しかし、ここ最近水郡線の臨時列車に乗り鉄する旅行でなければ水郡線を利用してない気が・・・
郡山に到着すると、側線にクルージングトレインの姿が確認できました。

一旦改札を出て知人と落ち合いしばらくして、再び改札口へ。
発車案内板の列車名表示は「臨時快速」でした。乗り場はごく普通に3番線です。


発車15分前に、一度車両基地方に移動し3番線に入線してきました。
 (拡大する)
(拡大する)
ホームに移動するとちょうど701系が入線してきたのでホームまたぎですが並びが撮影出来ました。
 (拡大する)
(拡大する)
引き続き出発前撮影をしていると、お見送りの横断幕がやってきました。
 (拡大する)
(拡大する)
車内に乗り込み、いよいよ出発!
郡山を出発すると磐城石川まで停車駅はありません!

乗客の大半はほぼ鉄道ファン。
席は最前列から2番目の席でしたが終始展望室には鉄道ファンで賑わっていました。
やはり水郡線常陸大子以北の多客臨はレアですし、さらに18きっぷシーズンであることが拍車をかけたのでしょう。
発車後カーブを抜けると郡山車両基地が見えてきます。
この日はE657系と14系客車の姿が見えました。14系客車はこれから解体されてしまうのかどうか気になるところです。

安積永盛は通過駅扱いですが、ここで少々運転停車をします。

安積永盛を発車すると東北本線としばらく並走し、新幹線高架をアンダークロスした付近で分かれます。

磐城守山を通過し、谷田川までの区間はほぼ直線で一面黄金色に染まりつつある田園地帯を走り抜けます。

谷田川からは勾配を登ります。

勾配を登り切ったところに位置する川東で、下り列車(327D)と交換をするため運転停車します。

川東発車後は磐城石川までノンストップ。しばらく走った後勾配を降り、国道118号線と並走します。
勾配を降りたところにちょうど福島空港の入り口があります。

空港の最寄り駅である泉郷を通過すると、あぶくま高原道路とアンダークロス。

野木沢通過後また軽く山道の様相となってきます。
またこの先トンネルをくぐっていきます。

磐城石川に停車。ここまでの所要時間は50分弱と普通列車と比較しても大差ありませんが、
クルージングトレインでの快適なシートのおかげで体感時間はあっという間でした。

磐城石川から先もところどころ勾配をアップダウンしながら進んでいきます。

次の停車駅である磐城棚倉はかつて白河とを結んでいた白棚線が存在していて鉄道路線廃線後はJRバスが引き続きバス路線として運転されています。
線路跡の一部をバス専用道に整備されており、言わばBRTの先駆け的存在とも言えますね。

棚倉の街の様子。写真の奥に宿泊やスポーツ複合施設であるルネサンス棚倉が位置しております。

近津通過。かつて対面式の構造だった跡が遺っています。

塙厚生病院が見えてくるとまもなく磐城塙

もっと乗っていたいところでしたが、ここで下車しなければなりません・・・
この駅で329Dの交換がありますが、川東と違って停車駅でありますので、撮影しようと乗車していた鉄道ファンらも撮影に車外へ出ていました。
 (拡大する)
(拡大する)
しばらくして、329Dが入線。
常陸大子方で待機していましたがかぶられてしまい、残念ながら並びは撮影できず・・・

329Dで引き返し帰路へとつきました。
乗車できなかった磐城塙〜常陸大子は東館より久慈川と平行しますので、その眺めを楽しむことができる絶景区間です。
また常陸大子以北を運転する水郡線臨時列車が運転された時には、全区間乗車したいです。
最後に車内で貰ったものなど。
沿線の観光パンフレット類が目立ちましたが、その他に水郡線活性化対策協議会オリジナルのクリアファイルと
須賀川のB級グルメ(?)のかっぱ麺というきゅうりの絞り汁で練り込んだ麺がプレゼントされました。
かっぱ麺は後日いただきましたが、付属のごまだれや味噌の味が強くきゅうりの味はほとんどなかったです。でも鮮やかな緑色の麺は見た目的にはいいかも知れません。

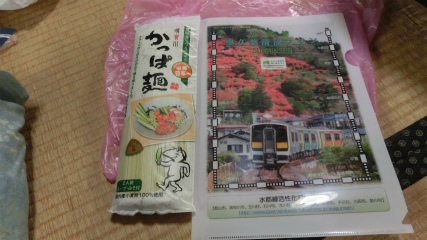
おわり



 (拡大する)
(拡大する) (拡大する)
(拡大する) (拡大する)
(拡大する)















 (拡大する)
(拡大する)